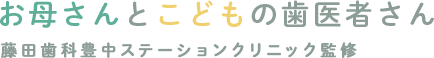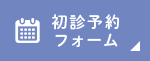今回は、乳歯の後ろから永久歯が生えてきた場合の対処方法についてご紹介します。乳歯から永久歯への生え変わりのタイミングはお子さまそれぞれで異なりますが、ごく稀に乳歯が抜けていないにもかかわらず永久歯が後ろから生えてくることがあります。予期せぬ状況に困惑してしまう保護者の方も少なくないかもしれません。そのような場合の対処方法を知っておきましょう。
●乳歯から永久歯への生え変わり
時期には個人差がありますが、5歳半から6歳頃になると乳歯から永久歯への生え変わりが始まります。乳歯が生えている状態の顎の中では、生え変わりの時期までの間に永久歯が少しずつ成長し、時期を迎えると乳歯の歯の根が少しずつ吸収されていきます。歯の根が吸収されると安定感がなくなってぐらぐらと揺れるようになり、やがて乳歯が抜け落ちると永久歯が生えてくる、という仕組みです。
●乳歯の後ろから永久歯が生えてくる?
しかし、稀に乳歯が抜けていない状態であるにもかかわらず永久歯が乳歯の後ろから生えてくることがあります。特にこれは下顎の前歯でよく起こることです。生え変わりの時期は顎がまだ未熟な状態なので、永久歯が自ら生えるスペースを探して乳歯の内側から生えてきます。
●乳歯の後ろから永久歯が生えてきたときの対処方法
乳歯の後ろから永久歯が生えてきたとしても、既に乳歯がぐらぐらしているようであればあまり心配はしなくても問題ありません。乳歯が自然に抜け落ちるのを待ちましょう。永久歯が生えてきてから2週間ほど経っても乳歯が動揺せず、抜けそうな気配がない場合は一度歯科医院を受診して相談してみてください。場合によっては乳歯の抜歯が選択されるケースもあります。また、乳歯の後ろ(内側)から生えてきた永久歯は徐々に正しい位置に移動していくのが一般的な動きです。しばらくは様子をみていても問題ありませんが、ある程度時間が経っても歯が移動しない場合も歯科医院での相談が必要になることがあります。
●まとめ
今回は、乳歯の後ろから永久歯が生えてきた場合の対処方法についてご紹介しました。乳歯から永久歯への生え変わりの時期はお子さまのお口の中をよく観察するようにし、適切に生え変わりが進むように見守っていきましょう。
お子さまのお口の中で気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。