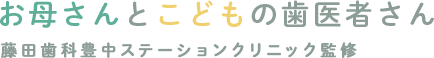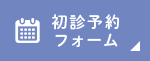街のあちこちがキラキラ輝く季節になってきましたね✨
これからクリスマスにお正月と、楽しいイベントが目白押し!
でも、甘いものを食べる機会が増えるこの時期こそ、歯の健康に気を付けたいところです。
そこで今回は「お子さまにおすすめのデンタルグッズ」をご紹介します!
子どもの歯は虫歯になりやすいです。ぜひ参考にしてください
★チャイルドケア★~歯磨き粉~
フッ素が入っているのはもちろん、含まれている甘味料の中で100%がキシリトールとなっています。
キシリトールは虫歯予防にとても大切!
また、これから当院で取り扱うパインとブドウはミント無配合です。ジューシーな香りでお子様も楽しくブラッシングできます。
発泡剤が入っていないので、お子様も使いやすいところもポイント。
★FLOSSY!★~デンタルフロス~
歯ブラシでブラッシングしただけでは、歯と歯の間は十分みがけないことがあり、プラークや食べかすが残ってしまいます。これらが虫歯の原因に!
歯ブラシでは届かない歯の側面についたプラークや、歯と歯の間に入り込んだ食べかすをきれいに取り除きましょう。
また小さい頃から歯間清掃の習慣づけをしておくと、大人になってからもより良い歯磨き習慣が身に付きます。
また、当院では、4か月から1歳6ヶ月のお子さまと保護者の方を対象にはみがき教室を毎月開催しています。
完全予約制になりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください♩(※)
小さなうちから、一緒にお子さまの大切な歯を守っていきましょう!
※当院の公式ラインにお友達登録後、メニューから「イベント」をタップし、フォームからお申込みください。当院に来院されたことのない方もお申込みいただけます。